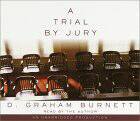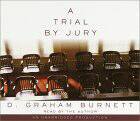|
一般市民が決める死刑
2000年5月に起きたハンバーガーショップ・ウェンディズでの強盗殺人は、ニューヨークの人なら誰もが知っている凄惨な事件だ。二人組みの強盗が閉店直後の店舗に侵入。7人の従業員を地下の大型冷蔵庫の中に並ばせて縛り上げ、一人一人の頭からビニール袋を被せて弾丸を打ち込んだという。頬を撃たれて死んだふりをしていたひとりと、重傷を負いながら奇跡的に助かったひとりを除いて、5人が死亡した。
2002年の10月末からこの事件の公判が始まり、メディアは裁判の模様を仔細に報道した。関心はニューヨークでは1953年以来の、死刑判決が出るかどうかだ。
裁判では「死刑で犠牲者の家族の苦しみを取り除くことは出来ない」とする弁護側と、死刑を求刑する検察側がそれぞれ、陪審員の情緒に訴える作戦に出た。
弁護側は被告人の未成年の子供たちを法廷に呼び、父親がどんなに自分を可愛がってくれたか、自分たちがどんなに父親を愛しているかを語らせる。子供たちは陪審員に向かい、「お父さんを殺さないで」と涙ながらに訴えたという。
これに対して検察は、事件当日の店内の模様を映す防犯ビデオを法廷で上映。生き残った二人の従業員も、ビニール袋ごしに聞いたことを証言した。
「裁判が始まるまでは、何も死刑にしなくてもいいと思っていた」と、後のインタビューで陪審員の一人は答えている。
しかし、「同僚は袋を被されて見えないまま、何が起きているの? 何が起きているの? と叫びながら撃たれた」という証言や、ビデオに耐え切れず、泣きながら法廷から逃げ出していく被害者の家族達の様子を目の当たりにして、「死刑の意義についても考えるようになった」とも。
そして、全員一致で死刑の判決が下された。
このウェンディズ事件の裁判は、私が陪審員制度をじっくりと見る最初の機会となった。一般市民から選ばれた12人の陪審員のプロフィールは、名前も、年齢も、人種も、職業もすべて情報公開される。彼らは世論の影響を受けないよう、裁判の間は情報から隔絶され、家族とも会えない。陪審員の情緒に訴えようとする法廷戦術は、時には感情的なしこりも生むだろう。
そんな状態で5週間も裁判は続いたのだから、陪審員を務めるのは精神的にも経済的にも相当な負担だ。
「だから、仕事や時間的制限を理由にして、陪審員を引き受けたがらない人は多いんだ」とアメリカ人の友達が教えてくれた。陪審員の義務を免除してもらう方法を教える、インターネットのサイトまであるとか。
検察と弁護側は自分達に都合のいい陪審員を選ぼうと攻防し、自分達の説得を鵜呑みにしそうに無い(知的な)人たちを選ばないとも言われている。
「どんな制度にも長短はあるけどね」
「自分自身は、陪審員にはなりたくないし、法律の専門家じゃない陪審員に裁いてほしくはないね」
私の周りのアメリカ人達は冗談めかして言う。
「子供たちにお父さんを殺さないでと言われた時が、一番辛かった」
「本当に正しいことをしているのか、何度も自分に問い掛けた」
「判決の時には、身体がガタガタ震えてしまった」と、死刑判決をした陪審員達は言う。
そんな場面にはできれば立ち会いたくないし、人の命を奪う当事者にはなりたくない…。
これがアメリカ人達のホンネだろう。げっそりとやつれた表情の陪審員をテレビで見ながら、私はそう思った。
|